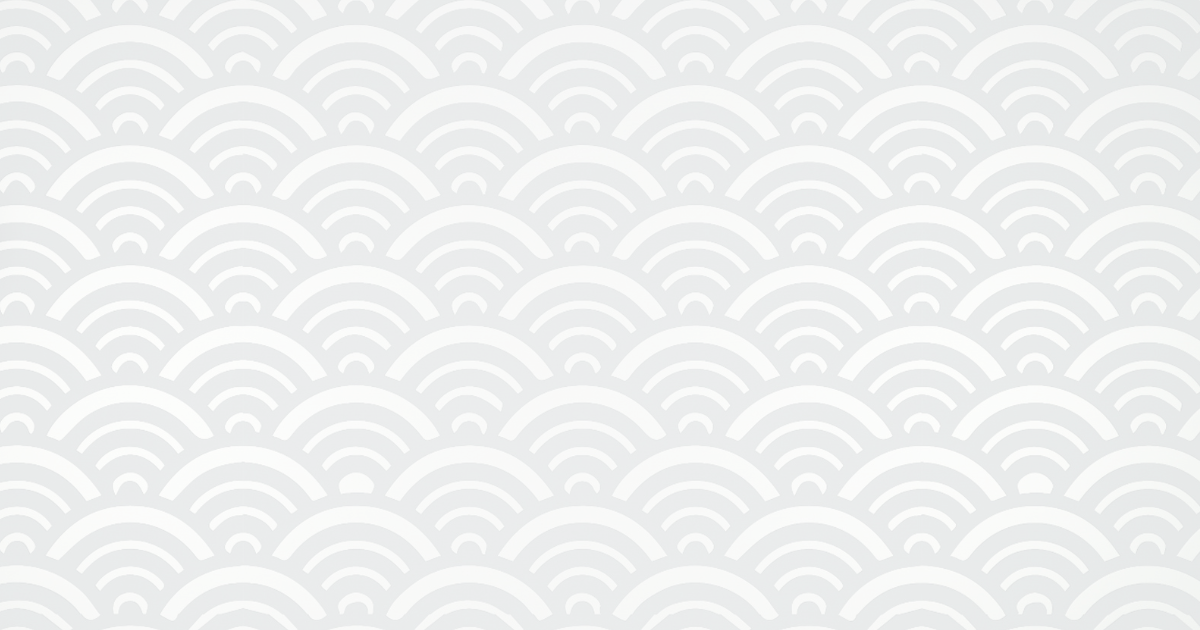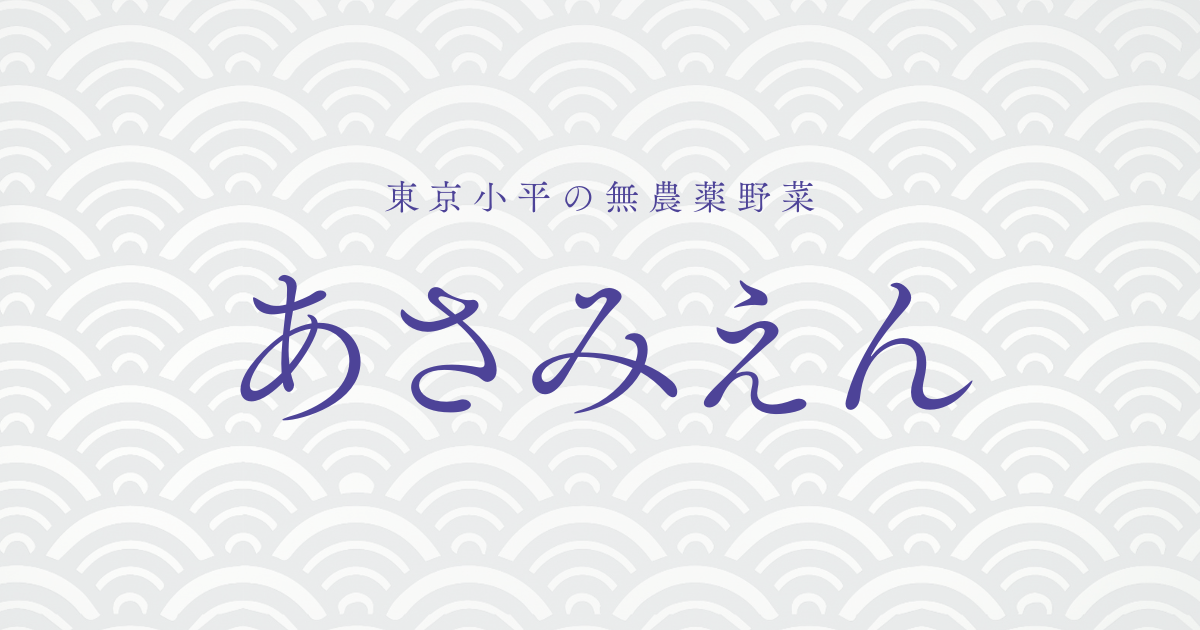炭素分を土中に浅くすき込む方法をずっと模索しています。
理想は以下の流れなんですが、現状内にはそれに適した機械がないため実現できません(特に2つ目)。
- 緑肥を育てる
- 機械で粉砕する
- 機械で浅く耕耘する
なので、以下の記述を参考に、薄く土で覆う手段をとろうかなとこれまた数年前に考えたのでした。
土の中で有機物を分解させると、最も効率的に団粒化します。表面に敷くだけでは非効率的で、少しでも早く一定水準の(最低限虫に食われない作物の育つ)土にしたい、転換初期には良い方法とは言えません。少なくともプロのやることではありません。機械力の無い家庭菜園では、薄く土で覆えば良いでしょう。
あわせて読みたい
そして現在、炭素分を土中に入れる方法をいくつか考えているんですが、その案の1つが、溝を切って入れる方法。
鍬で適当な深さの溝を切り、そこに枯草やら有機物を入れ、土をかけておく。
このやり方だったら、
- 有機物は土と触れるし
- 深すぎなければ酸素も足りるだろうし
- 土で覆えば水分も足りる
んじゃないかと。
で、じゃあ適当な深さってどのくらいだろうって、改めて調べ直して以下の記述を再発見しました。
混ぜる深さは通常、10cm前後で十分。特にキノコ廃菌床は最初から大量に酸素を消費するため常に浅く混ぜます。但し、有機物の処理能力の低い転換初期、腐敗が心配(判断できない)ものは敷くにとどめます。団粒化が進めばそれに合わせ、有機物を次第に深く入れても構いません。順調に土壌改良が進めば初年度10cm、2年目から5cmずつ深くし、最終的には通常の機械で可能な、25cm程度まで。
URLは同上
10cm前後で、その後、団粒化が進んだら深くしていくのもアリ、と。
で、これ実際に昨年(2023年)秋に、溝を切って草を埋めるということをやってみました。
その感想は、
溝がある程度深くないと枯草が入っていかない。少しの草でも簡単にあふれ出る。土をかけるなんて無理。
という具合でした。
平鍬で10cm程度の溝を切って、枯草を入れたんですが、彼ら結構かさがあるので溝に収まりきらないんですよね。
草があふれているから、土をかぶせる作業も非常にやりづらい。
で、じゃあもうちょっと深くしてみようかと20cm程度の溝にしてみたところ、いい感じに草を入れることができました。
が、そうなると不安なのが、酸欠にならないかな?という点で。
実際、つい最近(2023年3月)に↑の深く掘った溝を確認してみたのですが、底の方に入れていた草はガッツリ原形を留めていました。
固い枝みたいなものを使っていたことや、実験の大部分が冬だったことも大きな要因かなとは思っていますが、でも分解されている様子はあまり感じられませんでした。
ただ、雨の後かな?ってくらいしっとり濡れていて、水分は確保できているようでした。
香りも腐敗臭のようなものはなく、カブトムシの匂い(で伝わります?)がしました。
ガッツリではありませんが、ちらほら白い菌も見えました。
こういう状態だったので、悪くはないのかな?とは思うんですが、もう少し溝を浅くしたり、覆土の量を変えたり、アレンジできるところはあるのかなって印象です。
なので、先の引用を参考に、溝を切るタイプの方法をもう少し工夫してみようと思います。