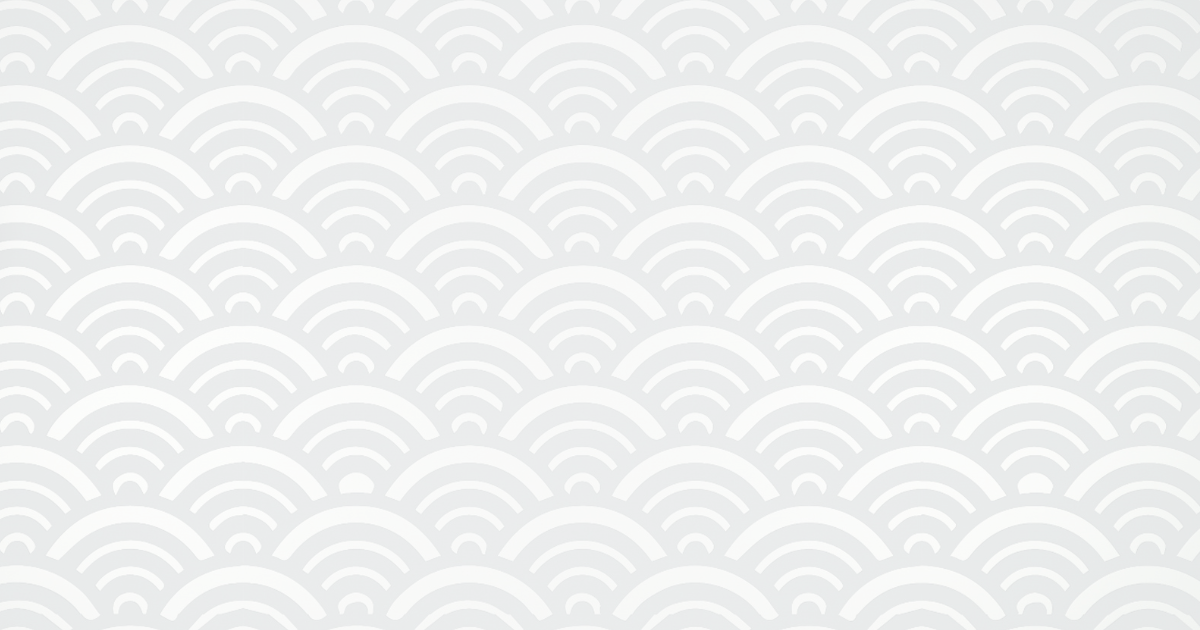畑の紹介
まずは畑の歴史や過去の状態を紹介します。
歴史
今から350年以上前(江戸中期)、徳川吉宗が享保の改革で新田開発を奨励していたころに、ご先祖がこの地に移り住んできたのが始まりと聞いています。
私の曽祖父(ひいじいさん)の代までは野菜の栽培をしていたようです。祖父と父の代は植木屋に転向。そして二人が亡くなった後、2020年からまた野菜の栽培に戻りました。
状態
面積は約7000㎡(約70a)。幅20m×長さ350mの南北に長細い畑です。
今でこそ無施肥無農薬栽培と謳っていますが、私が畑に出る2020年以前は、化成肥料も除草剤も殺虫剤も普通に使われている畑でした。だったからだと思いますが、そこから1~2年はまともに草が生えませんでした。トラクターによる耕うんと化学製品の使用が草の生えない環境を作ったのだと考えています。
当初は自然農だった(1~2年目)
私が畑に出始めた2020年は「自然農」というやり方をしていました。
自然農関連の本では「土が裸にならないように枯れ草を載せておきましょう」という文言がよく見られるのですが、畑に出始めたころは、その草がありませんでした。
これは自然農に取り組み始めた人にありがちな話なのかもしれません。畑に草が生えていないので、畝を立ててもかける草がありませんでした。ただでさえ畝立てして土を動かしているのに、その上を被覆するものがないですから、土はドンドン乾燥していきました。(元々水はけのよい土地だったというのも大きいです。)
もう一つ、私を悩ませ続ける問題がありました。強風です。これはうちの畑特有の問題なのかもしれませんが、夏以外の季節に強い北風/南風が吹きます。
強風の何が問題なのかというと、土の乾燥を加速させていくのです。畝の土は草で被覆されていない裸の状態ですから、強風によってドンドン乾燥していきました。乾燥し過ぎて困るので、なんとか畑中から草をかき集めてきて畝上に置いておくのですが、これがまた風に飛ばされるのです(笑)
ですから、畑に出始めた頃(2020~2021年)は、強風→土が乾く→防ぐために草をかける→風で飛ぶ→土が乾く、の地獄ループでした。
好転の兆し(3年目以降)
そんな地獄ループが改善されてきたのが2022年でした。諸々転換期になった年だったと思います。
畑のあちこちに緑が現れるようになりました。茎の太い、固くて強い草が多いですが、そんな草でも生えてくれるのはありがたかったです。草が生えるようになった理由は、2020~2021年の活動の成果ももちろんあるとは思うのですが、いちばん大きかったのは「おがくず」だと思っています。
おがくずと炭素循環農法
実は、この年(2022年)からおがくずをいただけるようなりました。おがくずというのは、ひのきや杉なんかを細かくパウダー状に砕いたものです。それをとあるお店から引き取らせていただけるようになりました。
炭素循環農法を知ったのもそのころでした。おがくず=炭素分=微生物のエサとして活用できる気がしたので、それらを畑の色んなところに混ぜ込みました。そしたら畑の色んなところからブワッと草が生えるようになったのです。
おがくずの効果が顕著に表れたのは畑の南側でした。それまで乾燥続きで草もろくに生えなかった場所に、おがくずをたらふくまいたところ、春から夏にかけてもっさり草が生えてくれました。そういう経験があったため、2022年→2023年の年始にかけて畑の随所におがくずを仕込みました。
自然農から手を引き始める
それからさらに炭素循環農法について調べました。なぜ無施肥で作物が育つのかを学び、実際に自分の畑でその効果を実感できました。そのような経験から、
「自然農は、理屈は素晴らしいのだけれど、実際に作物が育つようになるには(2~3年とかじゃなく)もっと長い年数が必要なのでは…」
と考えるようになりました。
しかも、この頃になると「お野菜買えますか?」とお話しいただくことも増えてきました。
自分一人で栽培実験をしていたころは、作物が育たないことも全然気にならなかったのですが、他者が関わってくると、毎回「ほとんど育たなくて…」と返事をするのもだんだん不甲斐なく感じるようになります。
そこで、自然農の原則を守る部分を畑の一角に確保しつつも、その他の部分ではおかくずを入れるなり、枯草をすき込むなり、積極的に変化を起こしていく実験を行おうと考えるようになりました。
このWebページやYoutubeで、当初は「東京の自然農 あさみえん」としていたのを、「東京小平の無農薬野菜 あさみえん」と変更したのも、上記のような考えの変化があったためです。
耕作している人紹介
あさみと言います。2020年1月頃から畑に出ています。
それまで農の経験はほぼゼロ。「ほぼ」としたのは過去に父の植木作業(根巻)を多少手伝った経験があるためです。野菜の栽培などは一切したことがありませんでした。
高校は普通科、大学は経済学部で、やはり農とは無縁でしたが、2019年に父が亡くなり、他に耕作できる人がいなくなったため、嫡男だった私が畑に出るようになりました。
自然農を始めたきっかけ
「どうして自然農をやろうと思ったんですか?」とよく聞かれます。最初の動機は手間を惜しもうとする不純な(笑)思いからでした。
確か大学3年生くらいの頃だったと思いますが、こんなことがありました。
→5月だ!せっかく畑あるしスイカ育ててみたいぞ
→よし、種買ってきたぞ!どうやってまけばいいんだろう?
→種袋「植え付け〇週間前までに㎡あたり石灰〇g、化成肥料〇gを施す」
→「え?どゆこと?…これって本当にやらなきゃいけないの…?いやいや、そんなことやらなくても育つ方法はあるでしょ。」
→『肥料 いらない 育て方』で検索
→自然農や自然農法の存在を知る
要は、5月のGWころに思いつきでスイカを育ててみたくなって、適当な種を買ってみたけど、種袋の後ろにごちゃごちゃ書いてあって「うへぇ」ってなった、という話です。
その後、自然農法を特集した雑誌のようなものを購入し、その本に従ってスイカの種をまいてみました。
しかし相手はスイカですから、何の準備もしていない土にポンと種をまいて育つはずもありません。結局そのスイカは発芽すらしませんでした(スイカ育てるの難しいのです…)。
スイカは育ちませんでしたが、「うーんこれは面白いぞ…!どうやったら肥料とか使わずに育てられるんだろう?」と農の世界にハマっていき、本を買ったりネットで検索したりを繰り返していました。
遍歴
2020年の最初の頃は、竹内さんの「自然菜園」と書かれた本をあてに緑肥ミックスをまいたり、燻炭をまいたりしていました。
しかし半年もたたないうちに、川口さんの自然農の方が好きだなと思うようになり、方向転換しました。
さらにその数年後、上述の通り自然農のやり方では変化が遅すぎると感じてしまい、2023年から現在にかけて、畑の大部分で炭素循環農法に近い方法を採っています。