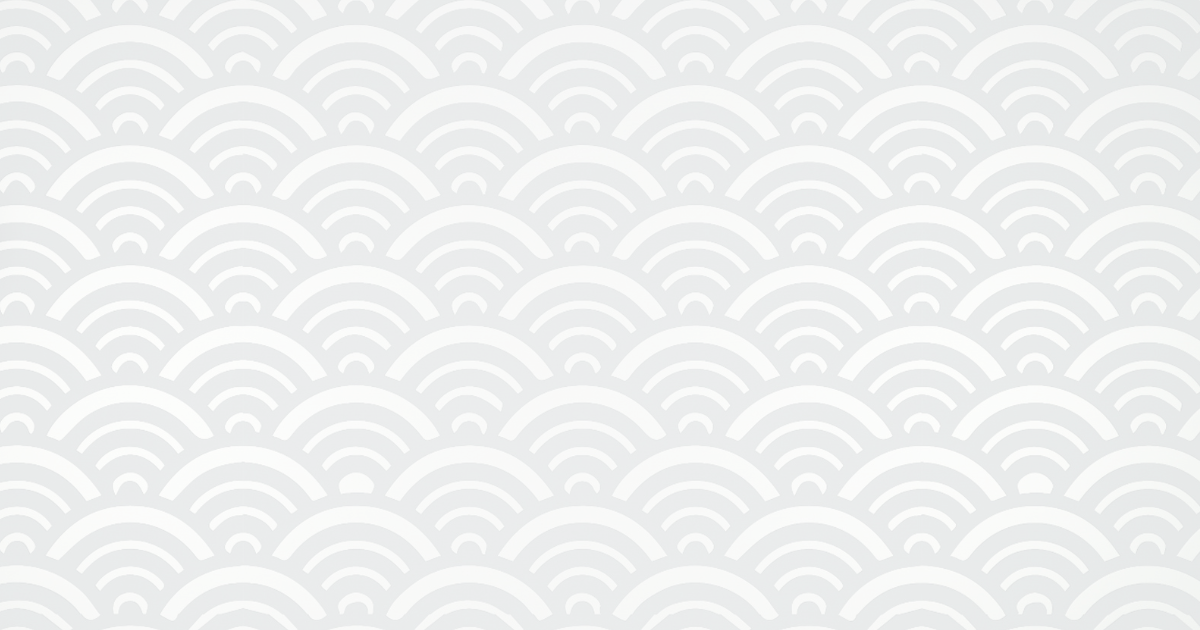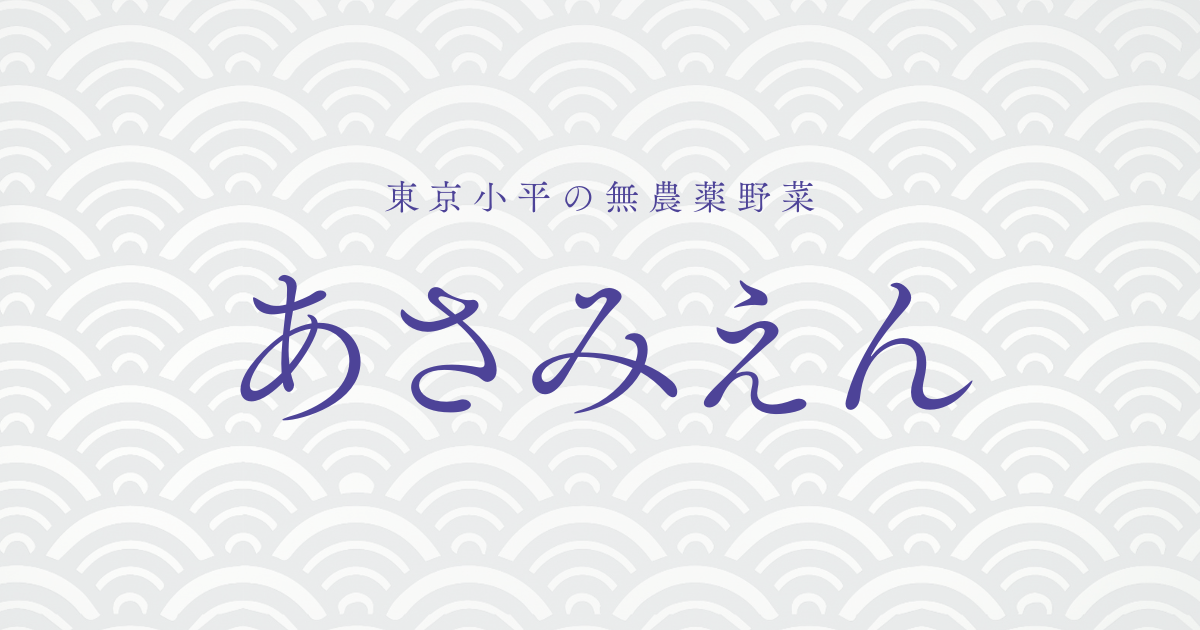今現在、あさみえんの畑は自然農の原則から外れてことをしています。
具体的には以下の2点です。
- おがくずを入れている(外から持ち込み)
- その際に混ぜている(耕していると言える)
1のために2をやっている(おがくずを入れるために土を動かしている)という感じです。
農薬や化成肥料を使うことはまずないのですが(※)、上記の点から自然農の考えとはズレてしまうなぁと思っています。
※2023年にウリ科野菜を育てるため、幼少期に酢と蛎殻石灰を反応させたものを吹きかけています(酢は農水省が指定する特定農薬なのです)
※比較実験用に化成肥料を使ったことがあります
なぜ上記のようなズレたことをやっているかというと、、、
うちの野菜を買いたいと言ってくれる人に「すみません、●●育てようとしたんですけど結局枯れちゃって…」というのが心苦しくなったからです(;´∀`)
2022年ころから、HPやYoutubeや口コミ等であさみえんの認知度が少しずつ向上していきました。
そしてそれと共に「野菜を買いたい!」という人が増えてきました。
しかし一方で、私はまともに作物を育てられていませんでした。
自然農の教本通りに畝を立て、生えてきた草を刈り、時折米ぬかと油粕を補っていましたが、ほとんどの野菜がまともに育たなかったのです。
育ったのは
- さつまいも
- 大麦
- オクラ
- アマランサス
くらいでしょうか?
しかしこれらも年によって育たなかったりと再現性がありませんでした。
「あさみさんは何をされているんですか?」
「自然農のやり方で野菜を育てています」
「え、買いたいです!」
「すみません…まだまともに野菜が育っていなくて…」
何度このやり取りをしたか分かりません笑
そんな折、おがくずをまいた(※)ところだけ、草の生えがやたら良いことに気付いたのです。
※おがくずは炭素循環農法でいうところの炭素分、つまり微生物のエサになるかなぁと考え導入したものでした
で。半信半疑でおがくずを入れたところと入れなかったところとで小松菜の生育比較実験をしたところ、
おがくずを入れた小松菜はきれいに育ち、
おがくずを入れなかった小松菜はそれまで通りボロボロに虫に食われたのでした。
これが2023年3~4月頃(※)の話です。
※これ以前から、つまり2022年冬ころからおがくずは使用していましたが、上記のような効果を実感していなかったのです。とりあえず炭素分入れておこうくらいの考えでした。
それからというもの、とりあえずおがくず入れておけばいい感じに育つのかもしれないと思うようになりました。
サニーレタスやほうれん草、アブラナ科全般、春菊等々、色々試しました。
ほうれん草こそ上手くいかなかったものの、それ以外の野菜は大変に元気よく育ちました。
以下の動画でアブラナ科の直まきが上手くいったと喜んでいますが、ここも事前におがくずを入れておいたところでした。
今のところ、私はおがくず=炭素分=微生物のエサという認識で使用しています。
- 微生物のエサを投入する
- 土中の微生物が増える
- 土が植物の生育に適した環境になる
- 3をある程度の期間継続する
- 外部からのエサの投入を止められる(以後は自然に循環される)
という考えです。
これはあくまで仮説なのでこの通り行くかどうかは不明ですが、今現在はこのような考えでおがくずを投入しています。
心配な点は…
- 上記5番目の段階にするのにどのくらいの期間がいるのか
- (同上)どのくらいのおがくずがいるのか
- おがくずは無機的に働いていないか
- 他の方はおがくずを入手できないので再現性がない
とかです。
なお、このおがくずはとある業者の方からいただいているものです。
先方は産廃を処理出来て、私は炭素分を無料でもらえて、いわゆるWin-Winの関係です(感謝)。