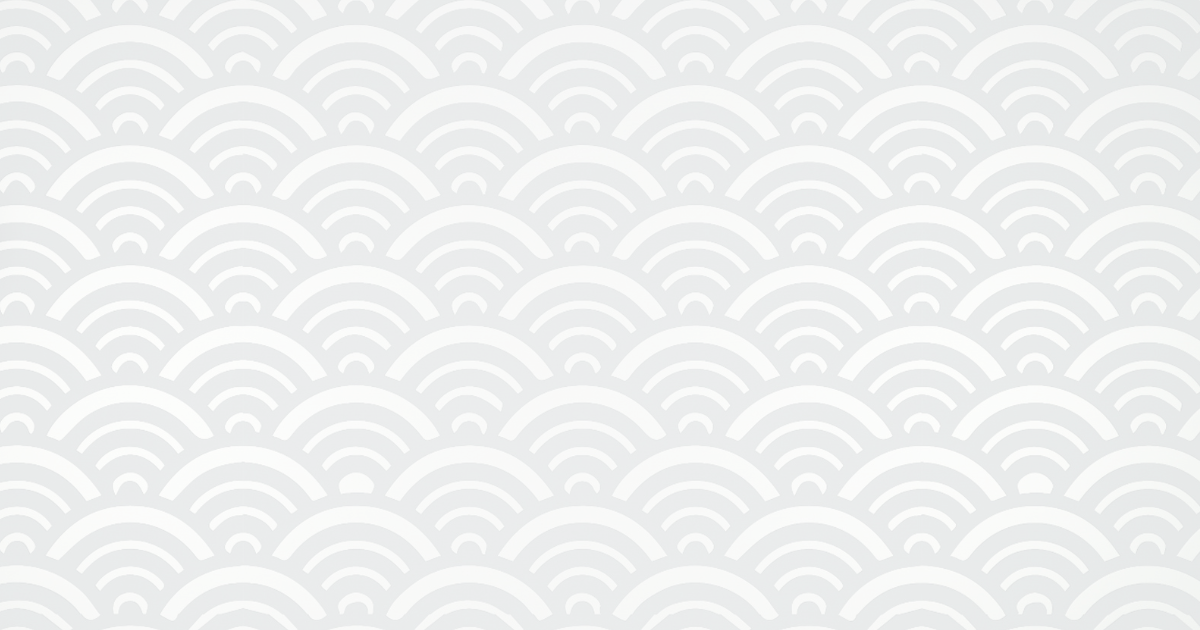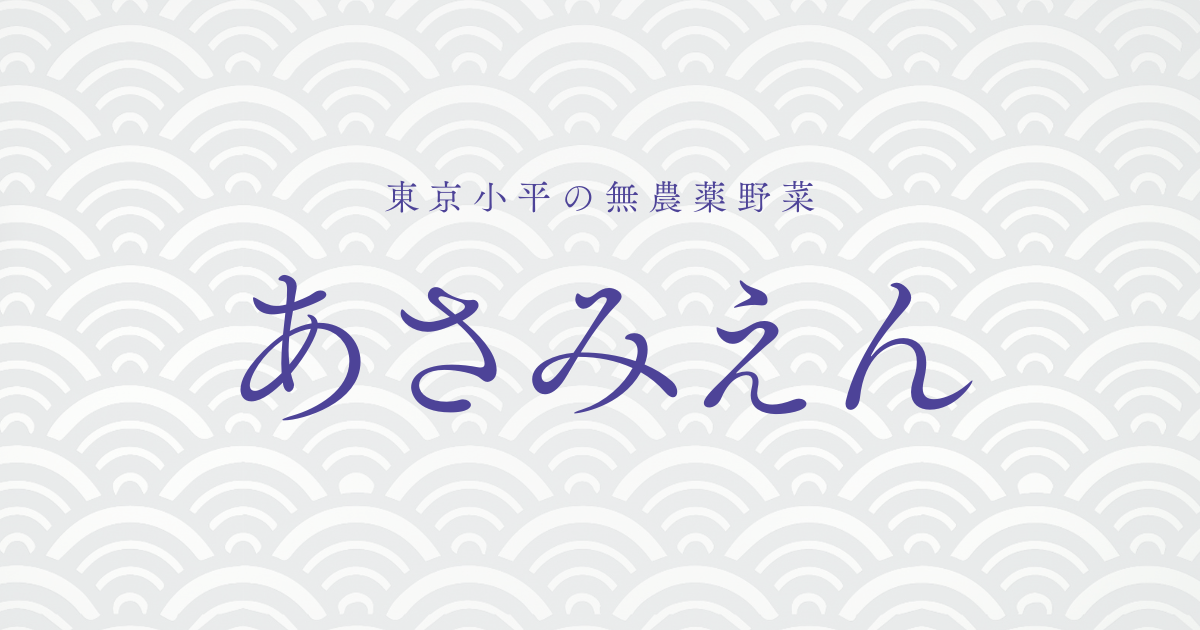浅見園の畑は、2019年まで慣行農法が行われていました。
ここでいう慣行農法とは、
トラクターなどで耕耘して、石灰・肥料を入れて、ビニールマルチを張って、農薬使って…
な日本中で見られるスタイルのことです。
なので、畑の色んな所をトラクターでかき回され、草があったら除草剤がまかれ、そうでなければ引っこ抜かれていました。
そういう状態から自然農に切り替えたため、当初は、というか2022年になった今でも”草が足りない”のです。
自然農の情報を発信している方がいます。
何十年も自然農を行い、そのエッセンスを一冊の本に凝縮して発信してくれるのは、大変ありがたいことなのですが…
まだ自然農に切り替えたばかりの畑では、根本的に草が足りないんですよね。
他所から草を持ってくるといい、と言われても、そもそも草の生えている他所を知らない。
敷地内にそんなに草の生えている場所がない。
まさか人の家の庭から草をもらってくるわけにも行かない。
ましてや浅見園のように、何千㎡もあると、ちょっとやそっとの草では足りないのです。
で、よく提案されるのが緑肥ですが、それも何千㎡をカバーするのにいくら必要になるのか…という問題があります。
ちなみに、乾燥しやすく、草すらなかなか生えてこない畑に緑肥のタネをまくときは、結構厚めに(=たくさん)やらないと焼け石に水です。
うちの畑の南側で試しました。
まだ自然農に切り替えたばかりの頃で、緑肥のタネをケチって播いたんですね。
そしたら全然面積をカバーできませんでした。
思い切って厚めにまかないとダメです。
で。
それじゃあお金をかけないで作物が育つようにするにはどうすればいいのか?を2年間悩み続けました。
基本的に自然界は、放っておけば草が生えます。
なので、畑に草を生やしたいと思ったら、放っておくのが一番確実だったのです。
が、農業委員会(役所)がそれを許してくれませんでした。
「それは生産していないだろう」
ということらしいのです。
「いやいや、将来スムーズに生産できるようにするために、今は草を生やしたいんです。放置しているように見えるかもしれませんが、これは戦略的に草を生やしているんです。」
と説明してもダメでした。
なので、自然に任せる作戦はなかなか取りづらい。
かといって、直まきを試みても、草すら生えない乾燥畑では、幼いうちにすぐに枯れてしまいます。
水をあげようにも、面積が広すぎてちょっと難しい(水ももったいない)。
そこで2022年から挑戦し始めたのが、苗の定植です。
直まきは幼少期の乾燥で枯れやすいのは先も書いた通り。
なので、ある程度大きくなるまでは手元で育て、それを定植してあげるようにする。
こうすれば、多少の乾燥にあっても、生き残る可能性はグンと上昇するはずです。
これはまだ取り組み始めなので、実際に上手くいくかはわかりません。
が、上手くいきそうな予感がしています。
この結果に関しては、追って情報を更新します。
また、大豆栽培にも挑戦します。
…いえ、大豆はこれまでにも挑戦してきました。
そこそこ株も大きくなりました。
が、豆を収穫できなかったのです。
理由は定かではありませんが、農書を見ると、開花時期に十分な水分が必要とあります。
もしかしたら過去の大豆たちは、この開花時期に乾燥にあってしまったのかもしれません。
開花時期は、種まきから2ヶ月後(60日後)らしいので、今年2022年は、その時期にピンポイントで水やり&草マルチを厚めに施してみます。
これで無事大豆を収穫できたら、大豆栽培が上手くいかない人への助け舟になるかもと期待しています。