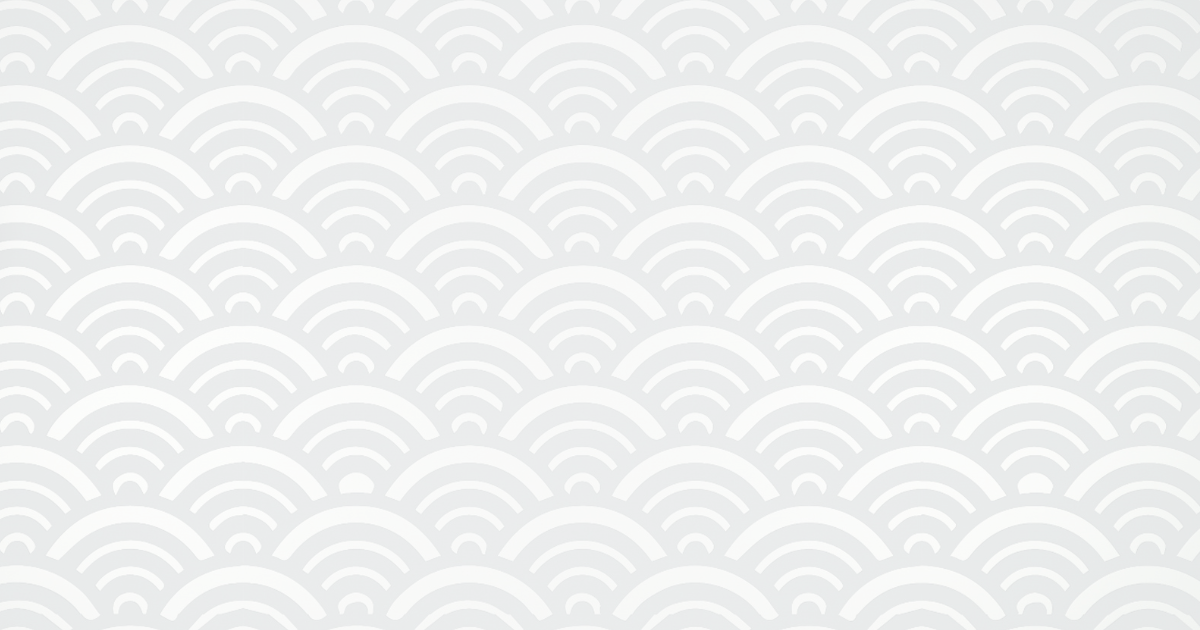野菜と果樹に分けて紹介します。
★ 野菜の栽培方法がアップデート…というか年々変化していまして、それに伴ってこちらのページの情報も更新しました(2024年3月15日)。
以前に(畑に出始めた初期の頃)どんな風に育てていたかを知りたい方は下の方までスクロールしてください(果樹は変わっていません)。
野菜
以下の2つの手法を行っています。
- 炭素循環農法を勝手にアレンジしたもの
- 菌ちゃん農法(試験的にごく一部の場所で)
炭素循環農法のようなもの
炭素循環農法そのものについては、こちらで詳しく説明しています。
炭素循環農法の考えでは、いかに土中の微生物を増やすかが肝です。そのために、土中に微生物が好む環境:空気/水/有機物を用意してあげる必要があります。
ここで問題になるのが有機物です。効率的に有機物を微生物に食べさせるために、緑肥や枯草を浅く土にすき込みたいのです。が、現在のうちの畑にある機材ではそれが上手く行えません。
ハンマーナイフという草を粉砕するマシンで緑肥を粉々にし、それを耕運機で混ぜるのが理想なのですが… うちにはハンマーナイフのような機械がないため、普通の草刈り機を使用するしかなく、けれどそれでは緑肥を細かくできないため、耕運機の刃に引っかかってしまうんです。
ですので現状、緑肥や枯草の代わりに、「おがくず」を炭素分として使用しています。
具体的な手順は、
- おがくずをまく
- 四本鍬でおがくずと土を軽く混ぜる
- 平鍬で鎮圧
ここまでやり、
- 直まきする(畑に直接種をまく)
- 育苗する(大きくなってから畑に定植する)
という具合です。
2023年までは育苗→定植のパターンが圧倒的に多かったです。直まきだと諸々の理由で失敗するからです。トマトやナスの果菜類はもちろん、キャベツや白菜、ほうれん草なんかの葉菜類すら育苗していました。
ですが、2023年の春~秋にかけて、直まきでも上手く育てられる方法を発見しました。それ以降は、ほうれん草や春菊などの葉物系野菜は積極的に直まきするようにしています。キャベツやブロッコリー、あとサニーレタスなんかは今でも育苗です。
あとあと。直まきにしても育苗→定植にしても、畑におろした当日とその後数日はほんの軽く水をあげています。これも数年前とは違う点です。
菌ちゃん農法
2024年3月から畑の南端で試験的に行っています。実際に作物を植えられるようになるまで3カ月ほどかかるらしいです。
もしこの方法で野菜がよく育つようになるなら、炭素循環農法よりも今のうちに適しているかもしれません。というのも、今はおがくずをいただけているから良いのですが、いつかおがくずをもらえなくなる日が来るかもしれません。そうなったときに、やはり緑肥や枯草を炭素分として活用できるようになっていたいのです。
が、先ほど書いた通り、機械を使わずに緑肥や枯草を土にすき込む上手い術が見つかっていません。
その点、この菌ちゃん農法は草刈り機で刈った程度の大きさの草を使いますから、緑肥や枯草を炭素分として積極利用できるんですね。なので、今やってる実験の如何は今後のうちの畑の状態を左右するものになるかもしれません(笑)
具体的な手順は
- 畝幅130cm、通路幅40cm、高さ50cm前後の畝を立てる
- その上に5-10cm程度の炭素分(枯草等)を載せる
- その上から2-3cm土を載せる
- ひと雨当てる
- 幅180cmのマルチを張る(ピンで50cm間隔でとめる)
- 土の塊をマルチの上にゴロゴロ載せる
です。
参考画像(畝立て段階)

参考画像(マルチ張り後)

幅180cmのマルチではなく、幅160cmのマルチを使用しているため、少し横が寸足らずです。あとマルチを止めているピンの手持ちが少ないため、80-100cm間隔で止めています。
以上です。個々の野菜の育て方はまだ実験中のためここでは記述しません。
果樹
果樹は切り上げ剪定に炭素循環農法の考え方を組み合わせて育成しています。
育てているものはこちらの記事で紹介しています。
具体的にやっていること
1:ビニールマルチ

まず植え付け時にビニールマルチを張っています。ビニールマルチとは写真にある黒いビニールシートのことです(真ん中の枝みたいのはリンゴの苗木)。
これを張ることによって、
- 土の温度が高くなり
- 土中の水分量が一定に保たれ
果樹の成長が安定するようです。
※ この理屈が正しいかどうかは分かりませんが、マルチ有り/無しで比較実験をしたところ、有りの方が良く育ちました。
あさみえんでは、ビニールマルチ等の資材はあまり使わないようにしています。
理由は
- 最終的にゴミになる
- 使わなくて育つなら使わない方が良い
と考えているから。
ですが、2021年2月に桃の苗木を植える際、ビニールマルチ有りと無しとで比較実験したところ、有りの方が圧倒的に生育が良かったのです。また、野菜栽培に使用するビニールマルチは、張り替えるたびにゴミになりますが、果樹のビニールマルチは一度張ってしまえば数年そのままです(=ゴミになりにくい)。
これらの理由から、2022年以降に植えるリンゴや梅の苗木の周りにはビニールマルチを敷いてます。
2:切り上げ剪定
冬になって葉が全て落ちた頃に果樹の剪定を行います。
すごくざっくりとした説明にはなりますが、以下のようなイメージで剪定しています(写真はブルーベリー)。
↓このような枝があったときに、

↓黄線の枝を残し、青線の枝を落とします。

また、↓のような枝があったときに、

↓青線の枝を落とします(黄線や緑線は残す)。

まだ私自身が剪定を勉強中であり、かつ木ごとに状況が違うので普遍的な基準を示すことはできません。
ですが、一応以下のような考え方で残す枝と落とす枝を決めています。
- 上方に伸びている枝は残す
- 下向きや水平方向に伸びている枝は落とす
- 太くて長い強そうな枝は残す
- 細くて短い弱そうな枝は落とす
このように冬の間に剪定しておき春~夏の間に収穫を迎えます。本来は夏の間に「夏季剪定」なるものをしておくと良いらしいのですが、夏季剪定についてはまだ分かっていないことが多く試せていません。
以上があさみえんで行っている野菜と果樹の具体的な育て方です。
==ここから更新前(20240315以前)の情報==
野菜
自然農と炭素循環農法の区域に分けて栽培しています。
各農法については、以下のリンク先で解説しています。
自然農での栽培
大まかな流れは以下です。
- 畝立て(初回のみ)
- 種まき(育苗の場合も)
- 状況に応じて草刈り
- 収穫
1:畝立て
初めにやるのが畝立てです。
畝というのは、作物を育てるために土を盛り上げた部分のこと。
自然農では周囲に溝を掘り、掘った土を盛り上げることで畝を立てます。

自然農の畝は、一度作ったらあとはずっと同じものを使い続けます(作り直す必要なし)。
崩れてきたら都度修正を繰り返します。人によっては十数年使い続けている人も。
2:種まき
種まきには大きく2つのパターンがあります。
- 畑に直接種をまく「直まき(じかまき)」
- セルトレイなどの容器に種をまいて苗を育てる「育苗(いくびょう)」
※ 育苗したものは、苗がある程度大きくなった時点で畑に植えます。これを「定植(ていしょく)」と呼びます。
【写真】直まきの例

【写真】育苗の例

直まきの方が作業自体が簡単で、かつ畑仕事っぽいイメージもあります。
ですが直まきで発芽→ある程度の大きさに育てるのは難しく、あさみえんではあまり積極的に行っていません。
難しい理由はいろいろあります。
- 発芽直後を虫に食われる
- 種まきした場所をケラに荒らされる
- 保湿管理が難しい
- 草取りが手間
これらの理由から、直まきで成功した経験があまりありません。
特に2番目の「ケラ」が非常に厄介と感じています。
ケラとは『ぼくらはみんな生きている~♪』に出てくるオケラのことです。
こやつらに何度も辛酸をなめさせられています。憎し(笑)
ですので、こうした問題の少ない「育苗」を選択することが多いです。
育苗だと手元で作物を育てられるため、
- 保湿管理が容易
- 虫から遠ざけることができる
- 比較的少量の種でたくさん苗を作れる
- 草取りの手間がほとんどいらない
など直まきのデメリットをほとんど解消できます。
定植の手間さえ嫌でなければ、非常に効率的な方法だと感じています。
3:状況に応じて草刈り
作物の周辺に草が生えてきたら刈ります。
すぐ脇に生えてくれば根元から刈りますし、そこまで近くないけど日陰を作るようでしたら、適当高さになるように刈ります。
作物の生育を邪魔しないレベルであれば放置です。
4:収穫
自然農の場合は、耕さない原則があります。
ですので、じゃがいもやさつまいもを収穫する際は、なるべく土を動かさないように配慮して掘り上げます。
また、例えばトマトなんかを収穫し終えた後の植物本体は、そのまま放置して枯れさせます。
枯れてきたら他の草たち同様、根元から刈り取りその場に敷いておきます。
敷いておくことでいずれ微生物たちに分解され、土を豊かにする材料になってくれます。
以上が、ざっくりとではありますが自然農の栽培です。
炭素循環農法での栽培
大まかな流れは以下です。
- 土中に炭素資材を入れる
- 種まき(育苗の場合も)
- 生育に応じて適宜草刈り
- 収穫
2~4は自然農と変わりありません(少なくともあさみえんでは同じやり方をしています)。
1:土中に炭素資材を入れる
炭素循環農法では、土中に「難分解性・高炭素資材」を入れることによって微生物(菌類)を繁殖させます。
細かい話は、炭素循環農法とは?を参考にしてください。
あさみえんでは作物の栽培前に炭素分として「おがくず」や枯れ草・枯れ枝を混ぜ込みます。
自然農のような畝立てはしません(栽培スペースを確保するのみ)。
一般の農業では、肥料や堆肥は作物植え付けの数週間前に土中に入れておくのがセオリーらしいです。
が、あさみえんでは植え付け直前でも構わず炭素資材を土中に入れてしまいます。
「え、それって大丈夫なの?」と思われたかもしれません。
実際私も、最初のころは「流石に直前はまずいかもなぁ…」と心配していました。
ですが、
- 大根
- 大麦小麦
- ほうれん草
- サニーレタス
- からし菜
- 白菜
- 玉ねぎ
等々の野菜が今のところ問題なく育っています。
なので、植え付け直前に入れても問題なかろうというのが現在の考えです(2022年12月時点)。
もしかしたら、よりよい投入タイミングがあるかもしれないので、そちらについてはおいおい研究していきます。
これ以降の、種まき→生育に応じた草刈り→収穫の流れは自然農と同じなので割愛します。